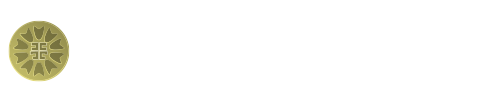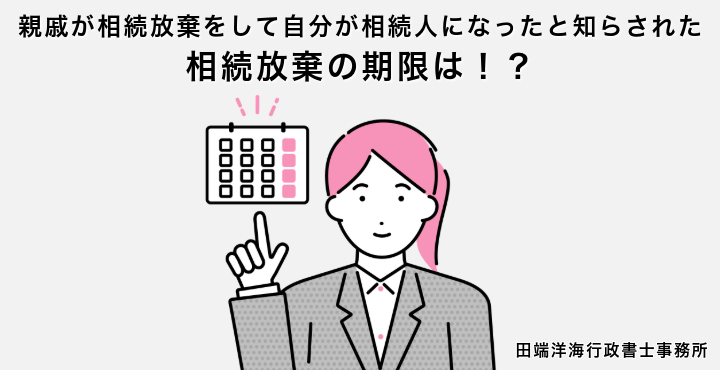ある日、長く連絡を取っていなかった親戚から突然の連絡がありました。
「父の子どもたちは全員、相続放棄をしました。そのため、父の兄弟である叔父さんが次の相続人になるそうです。でも、父には財産どころか、事業の失敗で多額の借金が残っています。叔父さんも相続放棄をした方がいいと思います。」そう告げられ、私も相続放棄をする決意をしました。
でもふと気になりました。「相続放棄って、たしか期限があったような……」
急に「放棄してください」と言われても、どうすればいいのか戸惑ってしまうのは当然です。
そこで今回は、相続放棄の「期限」について、わかりやすく解説していきます。相続トラブルに巻き込まれないためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
相続放棄とは?
民法では、人が亡くなると同時に相続が開始されると定められています。
相続が始まると、該当する人物は「相続人」となり、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利が生じます。ただし、相続の対象はプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
もしもマイナスの財産が大きければ、相続したくないと考えるのが自然でしょう。そうした場合のために、「相続放棄」という制度が設けられています。やや極端な言い方をすれば、相続放棄をした人は、相続に関しては亡くなった方と“法律上まったくの他人”と同じ立場になるのです。
相続放棄できる期限は?
相続放棄ができる期間は、「相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内とされています。
この「知った時」とは、一般的に被相続人が亡くなったという連絡を受け、自分が相続人であることを認識した時点を指します。被相続人の死亡日から起算するものではない点にご注意ください。
たとえば冒頭のケースでは、兄弟の子供から「私たちは相続放棄をしました。次はあなたが相続人になります」といった連絡を受けた時点で、自分が相続人であることを知ったと判断されます。その日から3カ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「申述書」を提出することで行います。申述は郵送でも可能ですので、遠方にお住まいの方でも問題なく手続きできます。
まとめ
今回の記事では、相続放棄の期限について分かりやすくご紹介しました。
突然の連絡で、疎遠だったご親族の相続人となったことを知り、対応に戸惑っておられる方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、相続に関するご相談も承っております。お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。