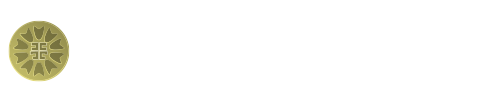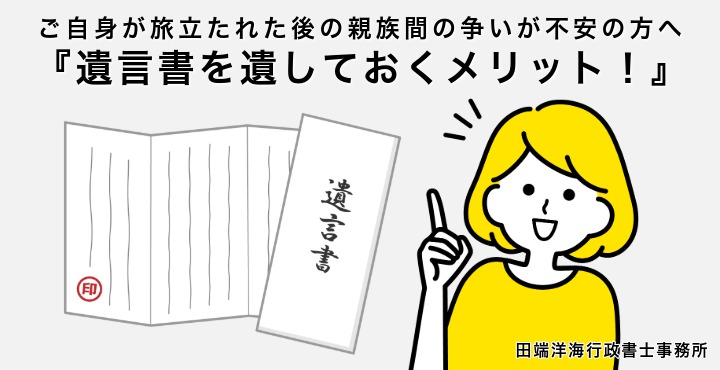自分が亡き後、相続財産をめぐって親族間でトラブルが発生するリスクがある。大事な親族がそんなことで争う光景を想像したくない。
相続手続きは大変らしいが、相続人の負担を軽くできないだろうか…。
「遺言書を遺しておけば良い」とたまに耳にするが、どんなメリットがあるのだろう…。
そんなお悩みをお持ちの方、今回の記事では遺言書を作成しておくメリットについて遺言書の作成方法の一例を挙げて解説します!
目次
遺言書とは?
遺言書とは、民法で定められた様式に従って作成することにより、遺言者(亡くなられた方)の希望する人に、希望通りの方法で財産を承継(譲り渡す)することができる仕組みです。
「希望する人」とは親族はもちろん、生前お世話になった友人や恩人なども含まれます。
遺言書の作成方法はいくつか定められていますが、一般的には次のいずれかの方法で作成されます。
- 自筆証書遺言:文字通り、ご自身で全文を手書きして作成する方法
- 公正証書遺言:公証役場で、公証人に作成してもらう方法
どちらを選択するにしても、遺言書の内容を決めるのはご自身です。
「財産を譲りたい特定の人もいないし、法定相続通りで構わないから、遺言書は必要ないかな?」
――ちょっとお待ちください。
実は、法定相続通りに相続させたい場合でも、遺言書を作成しておくことには大きなメリットがあります!
法定相続通りに相続させたい場合でも遺言書を作成しておく大きなメリットがあります!
法定相続通りに相続させる場合でも遺言書作成のメリット
民法で規定された通りに財産を承継させたい場合にも、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
民法では、亡くなった方に近い相続人から優先的に分配されるよう、相続の順位と割合が定められています。
以下は配偶者が生存している場合の相続分です。
| 配偶者相続分 | 各順位相続分 |
| 配偶者1/2 | ① 子1/2 |
| 配偶者2/3 | ② 親1/3 |
| 配偶者3/4 | ③兄弟姉妹1/4 |
配偶者がおられない場合は順位が上の相続人が財産を相続することになります。
※①の子がいる場合は、②の親や③の兄弟姉妹は相続人になりません!
この作成方法のメリットですが、相続人間の争いを発生させるリスクを回避できる可能性が高くなることに加えて、金融機関への預貯金の払戻し手続きや不動産登記の関係で被相続人と相続人の戸籍収集する作業が大きく簡略できます。
特に相続人が兄弟姉妹の場合は収集しなければならない戸籍が多くなりますので、相続人の相続手続きに関する負担をグッと減らすことになるでしょう。
まとめ
今回の記事では、遺言書を作成しておくメリットについて、一例を挙げて解説しました。
遺言書を遺しておくことで、相続人間の争いを防ぎ、エネルギーを消耗する相続手続きを簡略化できるという大きな利点があります。ぜひ、この機会に遺言書の作成を検討してみましょう。
当事務所では、遺言書作成サポートを行っております。「作成方法がわからない」「どの形式を選べばよいか迷っている」といった方は、どうぞお気軽にご相談ください。