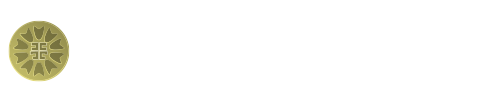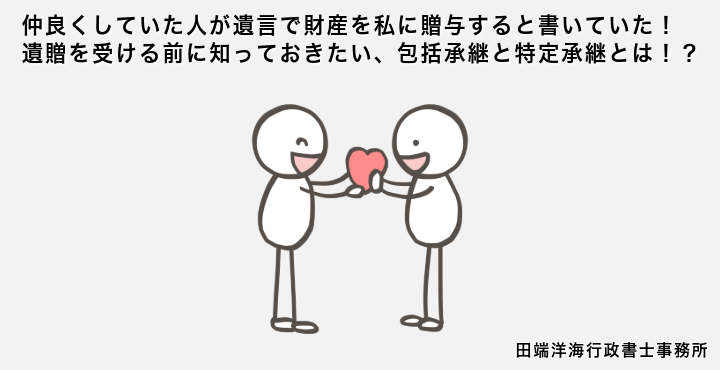付き合いの深い人が亡くなり悲しんでいたところ、亡くなった人は遺言書を遺しており、私に財産を贈ると記載されていた!このようなケースになった場合、亡くなった人の気持ちを汲み素直に受け取りたいところですが、場合によっては大変なことになるかもしれません!今回の記事では遺贈の特定承継と包括承継の違いについてわかりやすく解説します!
目次
特定承継とは?
人から権利や物を譲り受けることを法律用語で承継と言います。そして特定承継とは譲り受ける権利や物がはっきりしている、つまり文字通り特定された財産を譲り受けることです。
例えば遺言書に
「私の亡くなった後、大事な自動車はAさんに譲ります」
「〇〇銀行の預貯金をAさんに遺贈します」
などの記載であれば譲り受ける物がはっきりしているので特定承継と言えます。
そして遺言書で特定された物を譲り受ける場合は相続人とはみなされません。この言葉は非常に重要ですので覚えておいて下さい!
※注意!特定承継でも法定相続人には上記の規定は適用されません!
包括承継とは?
遺言書の内容が
「私の財産の半分を遺贈します」
「A男とB女には財産の3分の1づつ相続させ、残りの3分の1はお世話になったCさんに遺贈します」
このように遺贈を受ける財産がはっきりしていない、特定されていない物を譲り受けることを包括承継と言います。包括承継した人を包括受遺者と呼びますが、包括受遺者は法律で相続人とみなされます。相続人とみなされるとはどういうことなのでしょうか?
相続人とみなされると?
亡くなった人の相続人(法律で定められた親族です)は亡くなった人のプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)を相続しますが、仮にマイナスの財産(借金やローンなど)があった場合、それらも相続することになります。つまり包括受遺者として遺贈を受けた場合、マイナスの財産も知らずに譲り受けてしまうリスクがあるのです。
もしこの記事を読んでいる方の中に遺贈を受けた方がおられるなら遺贈の内容が特定遺贈か包括遺贈かを判断する必要があります。遺贈の内容が包括承継だった場合は相続の開始を知った時から3カ月以内に遺贈を承認するか放棄するかの決断をしなければなりません。遺贈を承認する方向で、亡くなった人の債務の状況を調べたい場合は信用情報開示請求制度などを活用しましょう。
ちなみに特定遺贈を放棄する場合は期限の定めは無く、遺言者の死亡後はいつでも遺言執行者や相続人に意思表示をすることで放棄が可能です。
まとめ
今回の記事では遺言書の内容による特定承継・包括承継の違いについて解説させていただきました。遺言書で遺贈を受けるということは亡くなった人とはかなり関係が深い場合が多いでしょう。
「できれば亡くなった人の気持ちを汲んで遺贈を受けたいが何か怖い・・・。」
こんな不安をお持ちになるかもしれません。当事務所では相続業務も扱っております。お一人で悩まず、どうかご相談下さい!